相続財産に賃貸不動産がある
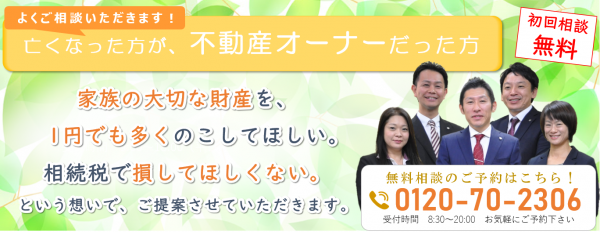
このようなお悩みございませんか?
・賃貸不動産を相続した場合にまず何をしなければならないのかがわからない・・・
・賃貸不動産は一般の住宅に比べて広いので多額の相続税が発生してしまうのか・・・
・賃貸不動産にローンが残っている場合でも相続した方が良いのか・・・
・賃貸不動産に空室が多いが相続した方が良いのか・・・
賃貸不動産を相続した場合にしなければならないこと
賃料の取り扱いについて決定する
賃料は毎月発生しますので、亡くなった月までは、被相続人の所得として確定申告をする必要があります。
それ以降の賃料は、相続した相続人の所得になりますので、相続人の確定申告が必要です。
相続する人か決定するまでの賃料は、誰のものか?
遺産分割が決定するまでは、法律で決められている相続分(法定相続分)にしたがって、賃料をわけることになります。
賃借人に連絡をする
オーナーが亡くなったままの状態では、口座が凍結して、賃借人が家賃を支払えなくなってしまったり、給湯器の修理など賃貸人としての義務が果たせなくなってしまったりする可能性があります。
すぐに相続人間で話し合い、代表者を決定し、賃借人との連絡係になる必要があります。不動産管理会社に依頼している場合には、管理会社に連絡します。
準確定申告をする
被相続人の生前の収入を相続人が確定申告してあげることを準確定申告といいます。
被相続人が亡くなってから4ヶ月以内に、申告をする必要があります。
金融機関に連絡をする
賃貸不動産のローンが残っている場合、金融機関にも連絡をしなければなりません。
誰が返済をするのか、そしてどのような形で返済をしていくのかを相談・連絡します。
ローンについて何もしないでいると、金融事故になってしまいますので注意が必要です。
また、被相続人が、団体信用生命保険(団信)に加入している場合もあります。その場合は、団信で支払うこととなり、負債は残りませんが、通常、団信の保険料が降りるのが2ヶ月程度かかり、その間のローンを支払わないと、金融事故になってしまいます。
賃貸不動産は一般の住宅に比べて広いので多額の相続税が発生してしまうのか
他人に土地や家を貸している場合
土地や家を人に貸している場合には、借主に借地権があるため自用地(自宅)よりも不動産の評価額が下がることが一般的です。
貸宅地の評価方法
これらを評価する上でのポイントは、借地(家)権割合です。この割合により、これらの評価額が変動することになります。
借地権は自用地としての価格に借地権割合をかけて求められます。貸宅地の評価額は以下の計算式で算出されます。
貸宅地の評価額 = 自用地としての価格 × ( 1 − 借地権割合 )
貸家や賃貸アパートの場合
貸家建付地の評価方法
貸家建付地は、自用地としての価格から借地権割合、借家権割合、賃貸割合をマイナスして評価されます。計算式は以下の通りです。
貸家建付地の評価額 = 自用地としての価格 ×(1- 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
賃貸割合とは
賃貸割合とは、宅地の全床面積に対して賃貸している部分の床面積の割合です。部屋によって広さが異なる物件の場合は、各部屋の床面積の合計に対して入居者のいる部屋の床面積の割合を算出します。一戸建ての貸家の賃貸割合は0%か100%になります。
賃貸アパートで小規模宅地等の特例を使うことも可能
以下の要件を満たせば、貸付事業用宅地等に該当して小規模宅地等のの特例を適用できます。
1.相続税の申告期限まで貸付事業を継続して行うこと
2.その宅地を相続税の申告期限まで売らずに、保有し続けること
3.相続開始前3年以内に貸付事業の用に供されたものでないこと(事業的規模であれば3年以内に供されたものでも適用可)
賃貸不動産にローンが残っている場合でも相続した方が良いのか
団体信用生命保険に加入している場合を除き、ローン(負債)も一緒に相続しなければならない場合が多いです。
ローンが残っていたとしても、その他の財産がとても多く、十分に負債を払ってしまえるのであれば、相続をすると良いかと思います。
また、ローンが残っている場合でも、収益性が高い物件であるか否かも考慮する必要があります。
賃貸不動産に空室が多いが相続した方が良いのか
立地もよく抜群の収益性があるということなら、問題ありませんが、空室もあるような物件の場合には、将来の世帯数減少による空室増加や、住宅過剰供給による賃料の下落なども考慮し、賃貸不動産を相続するのか否か、もしくは売却を検討された方が良いでしょう。
また、原則として、空室部分は貸付事業用宅地等から除外され、小規模宅地等の特例の適用が受けられません。例外的に空室前後1ヶ月程度で新たな賃借人に賃貸しているといった場合には、その空室は「一時的」であり、貸付事業を継続していると認められるため、特例の適用対象となります。
まずは、一度、専門の税理士へご相談されることをお勧めいたします。


