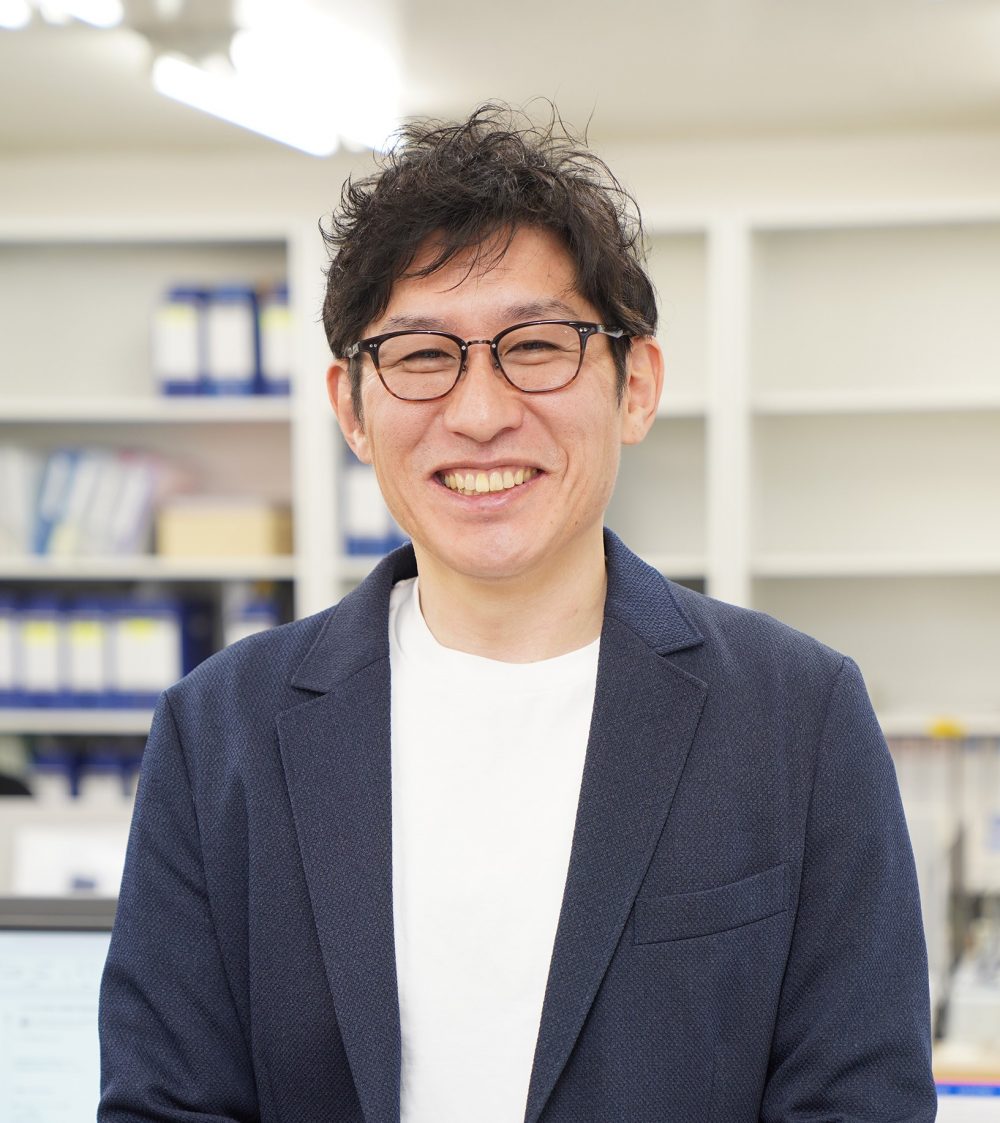#76 エンディング・ノートについて
終活の一つとして注目されているエンディングノート
最近では書店や文房具店などで購入ことができ、以前より身近なものになっています
エンディングノートにはどのようなことを書いておけばよいのでしょうか
今回はエンディングノートの基本について簡単に説明します
エンディングノートの基本
相続について何の準備もしないままに突然相続がおきてしてしまった場合、
相続人はまず、法定相続人を特定し、相続財産を調べあげなければなりません
しかしこれらは、亡くなった本人であれば容易に知り得た事項だったとしても、実際に手続きをするときにその本人はいません。本人を抜きにして相続人が調査や収集を行わなければなりません
相続放棄をするのかどうか、
準確定申告や相続税の申告手続、
相続手続きの中には期限のあるものもあり、のんびりしてもいられません
相続は一生のうちに何度も経験することではありません
相続人は手探りで膨大な相続手続追われることになってしまいます
エンディングノートは、書き遺す本人のためというよりは、遺された遺族の負担を減らすために遺族のことを思って書き遺しておくべきうものといえるでしょう
エンディングノートは、必ずしも法的効力を伴うものばかりを書くものではありません
細かいことで悩む必要はなく、たくさんの情報を書き残すこともできます
エンディングノートの書き方の具体例
エンディングノートの形式に決まったものはありませんが、たとえば次のようなことと書き遺しておくとよいでしょう
今所有している財産(借金がある場合や、他人の連帯保証人になっている場合などは、その内容もすべて)
自分を中心とした家系図(再婚している場合や婚外子がいる場合も書いておく)
税理士や司法書士など、日頃から相談している専門家がいる場合はその情報
法律上きちんとした遺言書を書き遺しているかどうか
市販のセレモニーノートには記入する項目が多いものもありますが、すべてを埋める必要はありません
大事なのは、まずはやってみる、ということだと思います
お知らせの最新記事
- #134 離婚と贈与 離婚が先か贈与が先か?
- #114 投資信託 メリットと基礎知識
- #113 相続時精算課税制度 その特徴と注意点
- 数字で見る相続 「マイナス0.5%」
- #105 「贈与」と「相続」 生前から考えておく節税対策
- #104 相続税額を算出するための相続財産の評価について
- #103 ローン返済中の親が亡くなったら残債は相続人が支払う?
- 数字で見る相続 「男性81.41歳 女性 87.45歳」
- #110 『お盆』 家族と話す相続・終活のこと
- #102 「配偶者居住権」の上手な活用
- #101 法定後見制度と資産運用
- 数字で見る相続 「0.5%下落」
- #100 教育資金の一括贈与制度
- #99 生前の不動産の分割
- #98 できるだけ多くの財産を現妻とその子に残すには
- #97 『相続欠格』『相続廃除』とは?
- #96 知らないと損する?二次相続を想定した遺産分割
- #95 遺産相続した相続人の確定申告が必要になるケースは
- #94 『令和3年度税制改正大綱』における相続税・贈与税の変更点
- #93 亡くなった年の確定申告『準確定申告』
- #92 相続税がゼロでも申告が必要?
- #91 85歳未満の障害者に適用される相続税の『障害者控除』
- #90 株式の相続手続においての注意点
- #89 未登記物件のデメリットと登記の手順
- #88 未成年者が相続人に含まれる場合、遺産分割協議はどうすればよい?
- #87 相続不動産を売却する際に受けられる特例
- 数字でみる相続 「60.1%」
- #86 民事信託を活用した財産承継
- #84 相続不動産を売却する際に受けられる特例
- 数字で見る相続 「21万5320件」
- #83 不動産の相続登記 必要書類について
- #82 知っておきたい「遺留分侵害額請求」
- #81 意外に多い「使途不明金」
- 数字で見る相続 「4592万円」
- #80 認知症対策としての成年後見
- #79 相続不動産の共有名義について
- #78 生命保険金の受取人が先に死亡していた場合
- #77 生命保険の受取人を誰にする?
- 相続税申告初めてで、不安でしたが、親切に対応していただいてありがとうございました
- #75 海外財産への日本の相続税の課税
- #74 株式を相続する際の手続
- #73 亡くなる3年前の贈与について
- #72 子の配偶者を養子にすることのメリット・デメリット
- #71 相続税についての問題の解決手段の一つとなる“生命保険”
- #70 せっかくの暦年贈与。名義預金とみなされないためには
- #69 遺言書の内容と異なる遺産分割はできない?
- #68 相続人と連絡がとれない?!相続手続はどのようにすすめればよいか
- #67 「遺留分侵害額請求権」について
- 数字で見る相続 「13.6%」
- #66 相続手続、スケジュールや期限は?
- #65 亡くなった親の借金を背負いたくない!『相続放棄』や『限定承認』で解決する
- #64 相続の手続を円滑にする「遺言執行者」のメリットと注意点
- Q&A 相続の対象となる財産とならない財産?
- #63 資産税の「令和2年度税制改正大綱」
- #62 相続対策の種類ごとの定申告時の要件や必要書類
- 東京都江東区 全て代行、訪問対応も可能
- #61 相続法の大改正。抑えておきたいポイント
- #60 遺産分割する際に不公平感が生まれるケース?
- #59 不動産を売買した方が1年以内にするべき税金手続は?
- #58 個人版事業承継税制とは?
- #57 空き家特例改正で老人ホーム入居も特例の対象に
- #57 『住宅取得資金贈与制度』とは?
- #56 配偶者に住む家を残したい!『配偶者居住権』とは?
- 数次で見る相続 「41.9%」
- セミナー開催 2019年10月11日/幕張テクノガーデン
- #55 『住宅取得資金贈与制度』について
- #54 生前贈与をする際の注意点
- 数字で見る相続 「93.7%」
- #53 エンディング・ノートについて
- #52 生命保険を活用した節税方法
- 相続準備(3)名義変更手続
- #51 財産を特定の人に託したいときに役立つ『民事信託』
- 相続準備(2)電子化財産の相続
- #50 相続準備としての事業承継
- ちいき新聞に掲載されました!
- #49 相続税のペナルティ⁉
- 相続準備(1)原戸籍の取得
- 数字でみる相続 「27年ぶり」
- セミナー開催 2019年5月23日・30日/千葉信用金庫 五井支店
- 相続・遺言 無料相談会!5月3日(月)~5月16日(日)
- #48 相続対策としての不動産の活用方法
- #47 不動産の「評価額」はどのように決定するの?
- #46『平成31年度税制改正大綱』 相続税・贈与税の主な変更点?
- セミナー開催 2019年2月21日(木)/京葉銀行 浦安支店
- Q&A 相続税の納税期間延長は可能?
- #45 相続税を滞納しないための節税対策
- 数字で見る相続 「314億円」
- 2500万円まで無税で贈与できる?「相続時精算課税制度」について
- 数字で見る相続 「1300件」
- Q&A 自分の財産をオーナー会社に贈与するときの税金?
- #43 夫婦間での自宅の贈与-おしどり贈与
- #42 新事業承継税制の入口要件
- 数字で見る相続 「3295億円」
- #40 遺言書の内容と異なる遺産分割協議はできる?
- #39 親から借りたお金が贈与に?
- 数字で見る相続 「2725件」
- 事業承継成功のために 〜事業承継は4つの視点に留意〜
- 平成30年度の税制改正によってなにが変わった? その1
- 子や孫への住宅資金の贈与 〜 利用したい2つの非課税制度とその注意点 〜
- 数字で見る相続 「4566億円」
- 相続の基本講座<相続税って何にかかる?>
- 数字で見る相続 「2兆1150億円」
- #31 遺産争いを防止する3つの準備
- #30 遺言書と遺留分は、どちらが効力がある?
- 数字で見る相続「99.93%」
- 数字で見る相続 「195.7万円」
- #29 「名義預金」とみなされないためには
- #28 子や孫の住宅取得をうまく活用しスムーズな財産移転を実現
- 不動産を共有すると、どんなデメリットがある?
- どんなに兄弟姉妹の仲が良くても、不動産を共有してはだめです!
- 高齢者の遺言書作成で気を付けるべきポイントは?
- 相続した実家を空き家のままにしておくことのデメリットは?
- その払い過ぎた税金、戻るかもしれません
- 「名義預金」は税務調査のチェックポイント!
- 相続登記について
- 相続放棄の期限がすぎてしまったらどうする?
- 公正証書遺言と自筆証書遺言 どちらがよい?
- 遺言がないとトラブルを招く「6つのタイプ」
- 次男にあらかじめ遺留分を放棄してもらうことは可能ですか?
- 相続対策って何をするの?正しい順番と考え方
- Q&A 孫のために預金口座をつくっている場合はどうすればいい?
- 相続税の税務調査はどう行われる?
- &A 仲が悪い兄に相続させないためにはどうすればいい?
- 「おひとりさま」の相続対策は遺言が不可欠!
- 「相続開始前3年以内の贈与財産」は相続財産に加算される!
- Q&A 「贈与税の配偶者控除」はどんなときに使えばいい?
- Q&A 不動産を共有すると、どんなデメリットがある?
- 「息子の嫁」に遺産をあげたい場合の4つの対策
- トラブルになりやすい「代襲相続」とは?
- 数字で見る相続「8.0%」
- なぜ課税対象者割合が倍増したのか?「身近になった相続」2つの対策方法
- 節税対策として注目が集まっている?孫を養子縁組にするメリットとデメリット
- Q&A 亡くなった父の連帯保証債務が発覚した場合、どうする?
- 相続・遺言 無料相談会 開催します! 2/2(金)、2/3(土)
- Q&A 死後離婚をすると、遺族年金や遺産などの相続権はどうなる?